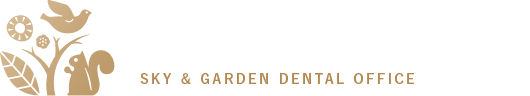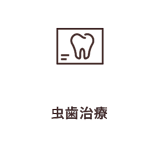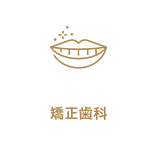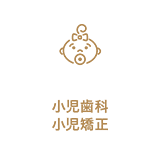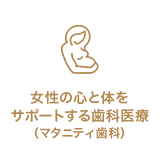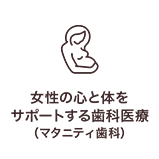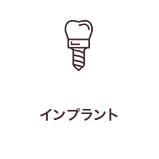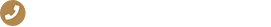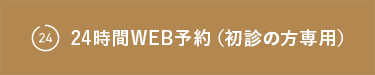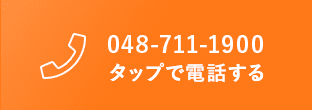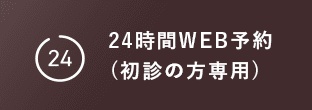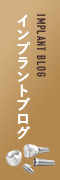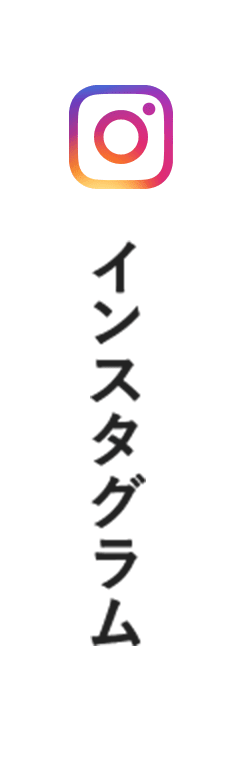入れ歯を長年使用している中で、「ずれやすい」「痛みがある」「しっかり噛めない」といった悩み感じたことはありませんか?以前の記事「入れ歯のトラブル『合わない入れ歯が原因で口内炎!』原因と対処法について」では、義歯が引き起こす粘膜トラブルの一例として口内炎を取り上げました。入れ歯は便利な反面、使い続ける中で様々な不具合を生じる可能性がある治療装置です。今回はその中でも、見逃されやすく、症状が進行すると治療が難しくなる「フラビーガム」という状態の特徴や発生のメカニズム、そして具体的な治療方法から予防策までを詳しくご紹介します。
フラビーガムとは何か?
「フラビーガム」は、日本語では「たるんだ歯肉」や「ぶよぶよとした歯ぐき」と訳されることがあります。歯を失った部位は、歯槽骨の上に歯肉(粘膜)が覆う形になりますが、その粘膜が異常に軟らかく変質する状態を指します。とくに上顎の前歯部分に見られやすく、軽く押すだけで変形するのが特徴です。肉眼で確認すると、周囲と異なる色合いや質感を持ち、押すと波打つように動くこともあります。そのため入れ歯がしっかりと安定せず、様々な不具合を引き起こします。
症状を引き起こす原因
この症状は、お口にフィットしなくなった入れ歯を長期間使用し続けることで生じます。入れ歯が粘膜に過剰な力を加え続けると、歯槽骨が徐々に吸収されてしまいます。それに伴って、歯肉の上皮は肥大し、線維組織の増殖が進行し、ぶよぶよとした状態へと変化していくのです。
特に注意が必要なのが、下顎前歯のみが残存している場合です。このような咬み合わせでは、上顎前歯部に集中的な圧力が加わるため、フラビーガムのリスクが高まります。たとえば上顎が総入れ歯で、下顎が奥歯のない部分入れ歯(両側遊離端)のケースでは、咀嚼のたびに前方に力がかかりやすくなります。さらに、長年使用した入れ歯が摩耗すると、咬合バランスが崩れ、前歯での接触が強くなります。その結果、上顎前歯部の粘膜が慢性的に刺激され、フラビーガムの発症リスクが高くなるのです。
フラビーガムが与える悪影響
粘膜が正常な弾力を失い、変形しやすくなることで、以下のような問題が起こります。
- 入れ歯が安定せず、違和感が続く
- 噛む力が分散され、咀嚼がうまくいかない
- 会話中や食事中に外れやすくなる
- 粘膜に痛みや傷が生じやすくなる
また、フラビーガムが広範囲に及ぶ場合、正確な型取りが困難になります。変形しやすい粘膜の状態で型を取ると、義歯の適合性が悪くなり、装着時にずれたり外れたりする原因となります。そのまま放置すると、あごの骨がさらに吸収され、症状が進行する恐れもあります。
適切な治療方法
フラビーガムの症状が確認された場合、次のような対応策が考えられます。
1. 外科的切除
増殖した柔らかい粘膜組織を切除し、顎堤の形態を整える処置です。切除後に安定した粘膜面が確保できるため、入れ歯の適合性がに向上します。外科処置は状態の進行度や部位によって適応が判断されます。
2. ティッシュコンディショニング
入れ歯の内面に柔らかい調整材を加えることで、粘膜に加わる刺激を軽減し、自然な回復を促す方法です。短期間で粘膜の形態改善が期待できるため、症状が軽度の場合に有効とされます。これらの治療は、単に入れ歯を新しく作り直すだけでは対処できないケースが多いため、粘膜の状態を正確に把握した上での処置が必要です。
新しい入れ歯作成時の注意点
治療をせず、フラビーガムをそのままにして義歯を作成すると、装着感や安定性に大きな支障が生じます。症状がある状態で入れ歯を作る場合は、かみ合わせの調整や型取りの工夫が求められます。細やかな診査・診断と、専門的な治療技術が不可欠です。
予防のポイント:入れ歯の定期的なメンテナンス
フラビーガムの発症を防ぐには、定期的なチェックと調整が重要となります。口腔内は日々変化しており、特に入れ歯は経年劣化とともに摩耗し、フィット感性が悪くなることがあります。新しい入れ歯であっても、最低でも3か月に一度は歯科医院で確認を受け、必要に応じた調整を行うことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。少しでも気になる症状がある場合は、早めの相談が大切です。快適に入れ歯を使い続けるためには、粘膜やあごの骨の変化にも配慮しながら、正しいケアを継続していきましょう。